2025年10月現在、医療費の自己負担がじわじわ上がっている。ニュースでも「高齢者世帯の医療費が家計を圧迫」という話題が増えた。うちの親も最近病院通いが増えて、「こんなに払うん?」と驚くこともある。でも、実は“高額療養費制度”や“医療費控除”など、公的な支援をうまく使えば負担をかなり減らせる。今回は、2025年最新の制度内容を整理して、知っておくと安心できるポイントを紹介するで。
0. 目次
1. 医療費が高額になった時に使える支援制度
2. 高額療養費制度のしくみと上限額(2025年10月版)
3. 医療費控除のしくみと計算方法
4. その他の支援制度(介護・自治体・民間)
5. まとめ:制度を知って“払える安心”を持とう
1. 医療費が高額になった時に使える支援制度
医療費が高くなったときに助けてくれる公的制度は主に3つあるで:
・高額療養費制度(医療費の上限を超えた分が戻ってくる)
・医療費控除(確定申告で税金が軽くなる)
・高額介護合算療養費制度(医療+介護の合計負担を軽減)
どれも申請しなければ戻ってこない制度やから、まず“知っておくこと”が大切や。
2. 高額療養費制度のしくみと上限額(2025年10月版)
高額療養費制度は、1か月に支払う医療費の自己負担が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度や。70歳以上かどうか、所得によって上限額が異なる。
| 所得区分(70歳未満) | 上限額(月) | 計算式 | 多数回該当後 |
| 年収約1,160万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 上位所得者 | 140,100円 |
| 年収約770~1,160万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 一般上位 | 93,000円 |
| 年収約370~770万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 標準層 | 44,400円 |
| 年収約370万円未満 | 57,600円 | 低所得Ⅰ・Ⅱを除く | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 低所得Ⅰ・Ⅱ | 24,600円 |
同じ世帯で複数人が医療を受けている場合は「世帯合算」もできる。また、過去12か月以内に3回上限額に達していれば、4回目以降は“多数回該当”としてさらに上限が下がる。
3. 医療費控除のしくみと計算方法
医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で所得から差し引かれる制度や。2025年も引き続き上限200万円、10万円または所得の5%のいずれか低い方を超えた分が対象や。
たとえば、年間医療費が30万円で保険金などの補填が5万円、所得が400万円の場合:
→ 控除額=(30万円−5万円)−(400万円×5%=20万円)=5万円が医療費控除の対象になる。
この分の所得税・住民税が軽くなるわけや。
【セルフメディケーション税制】
市販薬を年間12,000円以上購入した人は、医療費控除の代わりに“セルフメディケーション税制”を使える。ドラッグストアのレシートに★印がついている医薬品が対象で、2025年度も制度が延長されてるで。
【申請のポイント】
・e-Taxやマイナポータル連携を使えば、領収書の提出は不要(データ添付でOK)。
・医療費の明細を「医療費控除の明細書」にまとめて提出する。
・保険金で補填された分は差し引くことを忘れずに。
4. その他の支援制度(介護・自治体・民間)
医療費が高くなったとき、上の2つ以外にも助けになる制度があるで。
・高額介護合算療養費制度:医療と介護の自己負担を合算して上限超過分を払い戻し。
・自治体の医療費助成:子どもや高齢者向けに上乗せ補助を行う自治体も多い。
・民間保険:医療費支払い後に入院給付金などでカバーできる場合も。
5. まとめ:制度を知って“払える安心”を持とう
医療費は突然増えることもあるけど、制度を知っておけば必要以上に心配せんでええ。特に高額療養費制度と医療費控除は、申請しないと戻ってこない仕組みや。家計を守るためにも、領収書やレシートは1年分まとめて保管しておこう。もし不安があれば、病院の窓口や市役所の国保担当窓口で相談してみるのがおすすめや。
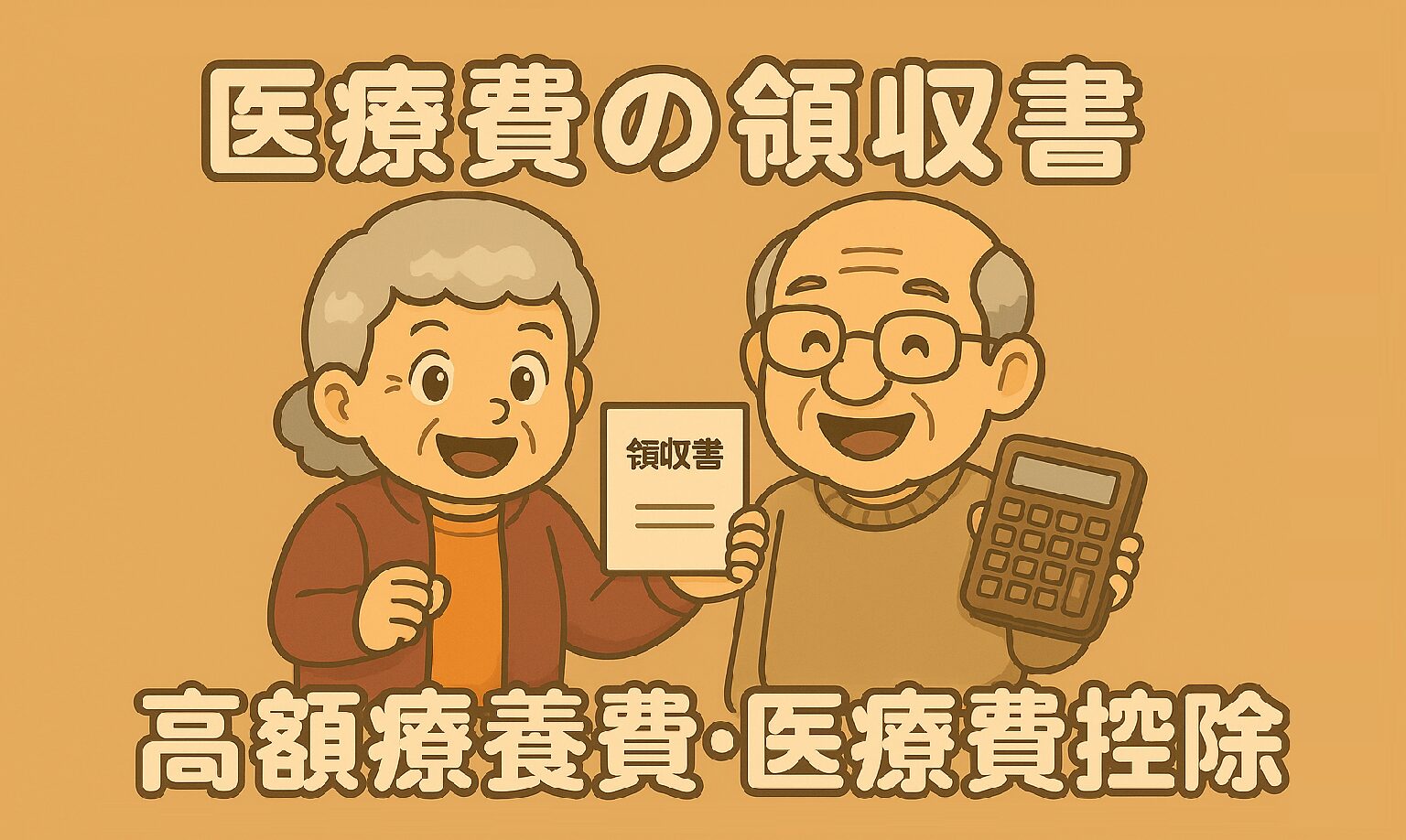

コメント